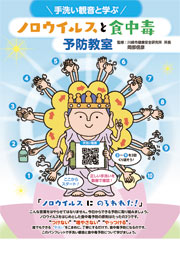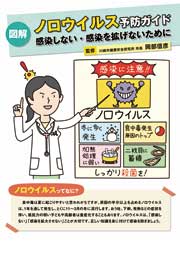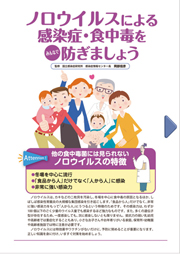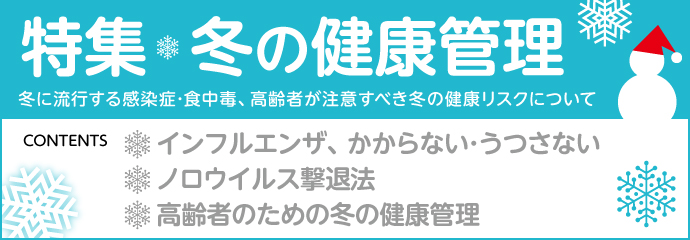
ノロウイルス撃退法
感染力が強いノロウイルス
ノロウイルスは食中毒の原因となるウイルスです。感染力が強く、わずかなウイルス量で感染するため、しばしば集団感染を引き起こします。ノロウイルスによる食中毒は1年を通して発生していますが、主にカキなどの二枚貝に含まれるため、消費が多くなる11月くらいから増えはじめ、12月から春先に集中して発生する傾向があります。
主な症状は、激しいおう吐や下痢です。感染後1~2日でこのような症状が現れ、人によっては発熱、頭痛などをともないます。
3つの感染ルート
ノロウイルスが人に感染するのに、3つのルートがあります。予防・対策とあわせて覚えておきましょう。
食べ物→人
ノロウイルスがついた食品や井戸水などの飲料水を飲食して感染します。
ノロウイルスが蓄積しやすい二枚貝(カキ、アサリ、ハマグリ、ホタテ、アカガイ、ホッキガイなど)を食べるときは「生食用」以外は生食は避け、中心部までしっかりと加熱しましょう。
人→食べ物→人
ノロウイルスに感染した人が調理した食べ物や、汚染された食品を調理した人の手指を介して感染します。
調理する人は、調理前に石けんでしっかりと手を洗いましょう。
ノロウイルスに汚染されている食品でも、加熱処理でウイルスを殺菌すれば、感染はしなくなるとされています。
加熱処理の目安:中心温度85~90℃以上で90秒間以上加熱する。
人→人
感染者の便や吐いたもの(おう吐物)、またそれらがついた手で手すりやドアノブなどに触れることで感染します。
乾燥したおう吐物に含まれていたウイルスがほこりとともに空気中に散って、感染を広げることもあります。
感染者の便やおう吐物は、すばやく確実に処理しましょう。
汚物処理の方法
もし感染が疑われたら
感染から1~2日でおう吐や下痢、38℃前後の軽い発熱などがあらわれますが、通常は3日ほどで症状が治まります。
おう吐や下痢が続くと脱水症状が起こりやすく、とくに乳幼児や高齢者は注意が必要です。おう吐が続いていたとしても、何回かにわけてこまめに水分を補給しましょう。
細菌や毒素を排出するためにも、下痢止め薬は飲まないようにします(整腸剤は飲んでもかまいません)。
横になった状態でおう吐すると窒息するおそれがあるので、注意が必要です。
医療機関の受診が必要な症状
- 明らかな血便や黒色便が見られる
- 黄色、緑色の液体を吐く
- 意識障害がある(刺激を与えてもすぐに寝る、ぐったりして抱きつくこともできない、けいれんするなど)
- 繰り返し激しい腹痛がある、繰り返し激しく泣く(乳幼児の場合)
- インフルエンザ、かからない・うつさない
まずは予防接種から。日常でできる、ウイルス感染予防方法をお伝えします。 - ノロウイルス撃退法
料理のときの注意は? もし吐いてしまったら? 対処方法を知っておこう。 - 高齢者のための冬の健康管理
気温差が命とりに! さらに冬に盲点となる「脱水症状」について解説。
< こちらもご参考に >
ノロウイルスと食中毒予防教室
手洗いの仕方や汚物処理の方法を動画でチェック!
図解 ノロウイルス予防ガイド
感染しない・感染を拡げないために
ノロウイルスの予防知識まとめ
これだけは知っておきたい決定版
ノロウイルスによる感染症・食中毒をみんなで防ぎましょう
一般家庭だけでなく、幼稚園・保育所や高齢者施設にもおすすめ